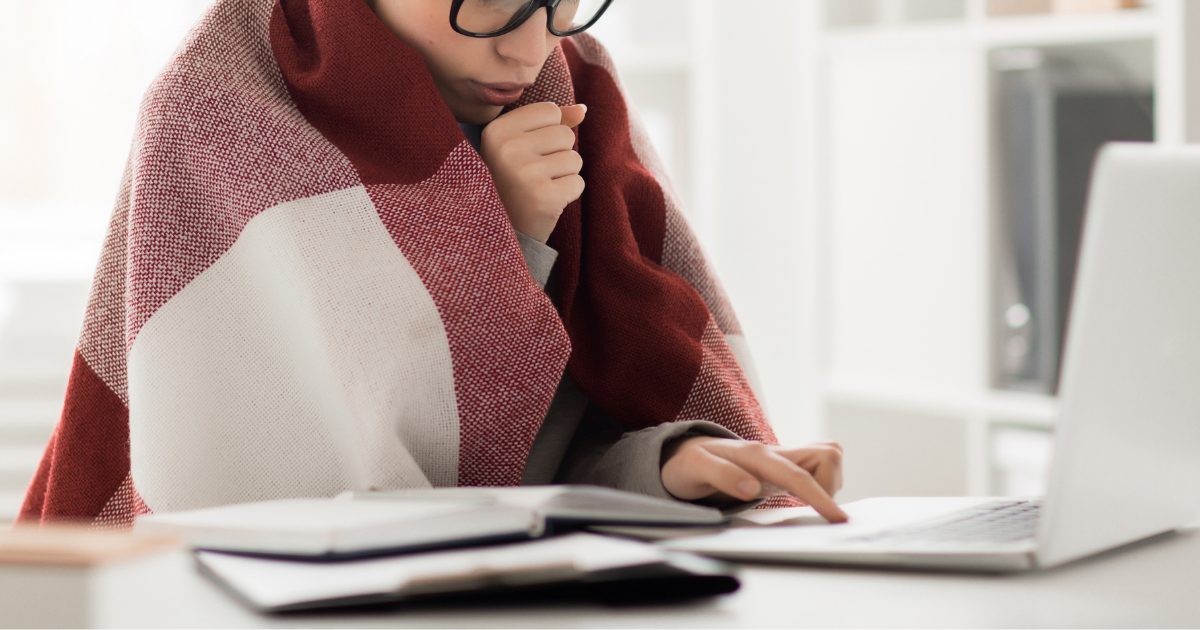毎日の仕事や家事に疲れてベッドで眠り、朝起きると、こんなことはありませんか?
「顔がパンパンにむくんでいる!!」
「目の周りが腫れてる!」
慢性的な疲労は、瞼や頬など顔のむくみにつながります。
また、女性にとって顔のむくみはメイクのりが悪くなるという大きな困りごと。
疲労をためやすい生活は、血行や水の流れを悪くし、顔のむくみの原因となります。
血行や水分の流れを良くしてあげることで、むくみ顔の対策となりますよ。
むくみとりのコツを押さえた生活習慣は、むくみだけではなく疲労の解消にも効果的!
まずは顔にむくみがでる理由を探っていきましょう。
疲労がたまると顔にむくみが出る理由とは
 むくみは医学的には「浮腫(ふしゅ・むくみ)」と呼ばれ、余分な水分が皮膚や皮膚の下にたまった状態を指します。
むくみは医学的には「浮腫(ふしゅ・むくみ)」と呼ばれ、余分な水分が皮膚や皮膚の下にたまった状態を指します。
基本的にむくみは一時的なもので、大いに関係しているのが生活習慣です。
そもそも、なぜ顔のむくみが起こるのでしょうか。
理由①水分の流れが滞るとむくみやすくなる
人間の体の60%は水分で出来ています。[1]
60%の水分のうち、体重比で見ると40%は細胞内に、20%は細胞外に存在。
細胞外液をさらに分けると、間質と呼ばれる細胞と細胞の隙間に15%、残りの5%が血液やリンパ液、脳脊髄液です。

血液と、細胞の隙間である間質の間で水分が行き来することで、細胞に栄養を送り老廃物を取り除くことができます。
水分の行き交うバランスが崩れて間質に水がたまった状態がむくみです。
一般的に足のむくみは、夕方に出やすくなります。
1日中立ったり座ったりしていると、重力で下半身に水がたまっていくからです。
一方で顔のむくみは起床時に出やすい傾向が。
これは横たわって眠っている間に、重力で顔に水がたまるためです。
また疲労で血流や水のめぐりが悪くなると、むくみ顔になることも。
最近増えてきているテレワークやデスクワークも顔のむくみの一因です。
理由②目の疲れで顔のむくみが悪化
デスクワークで長時間パソコンを凝視すると、眼輪筋という目元の筋肉の疲労を引き起こします。
眼輪筋がこると、血液やリンパの流れが悪化し、目の周りに水分や老廃物が。
これがまぶたのむくみの原因です。
眼輪筋はスマートフォンの見過ぎでも疲れてしまいます。
翌朝のすっきりした目元のためには、眠る直前にはスマートフォンを触らないのがおすすめです。
むくみの理由を知ってスッキリした毎日を
 顔のむくみの理由を解説しました。
顔のむくみの理由を解説しました。
- 水分の流れの悪化
- 目の疲れ
他にも生活習慣なども、むくみにつながることも。
むくみの理由を知って、スッキリした毎日を過ごしましょう。
【参照】